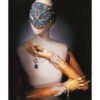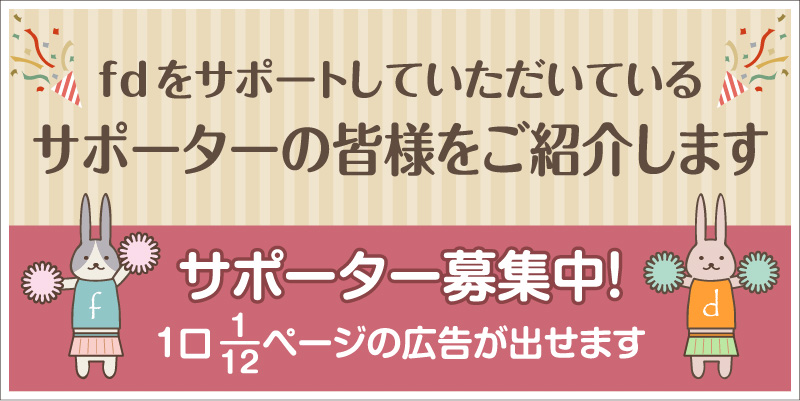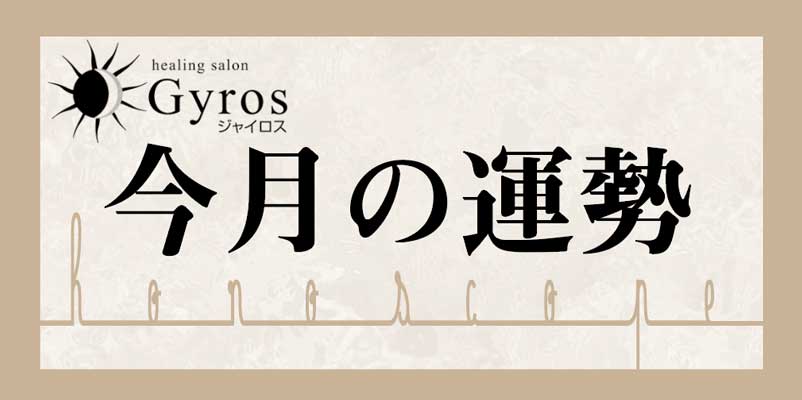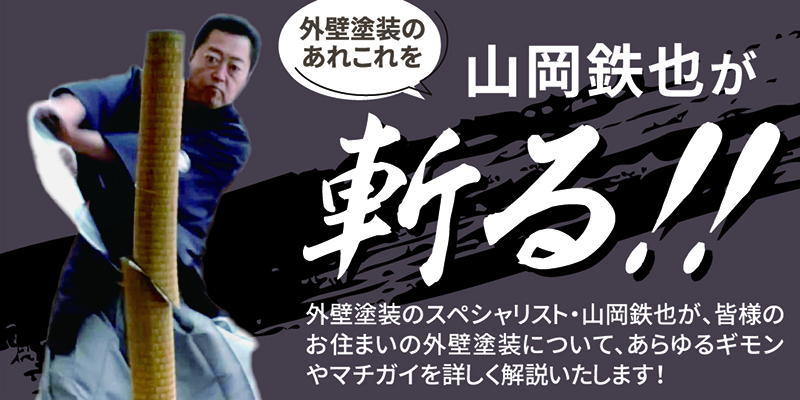南京町にある行列店と聞けば、神戸っ子の頭に真っ先に浮かぶ「老祥記」。寒空の下でもうだるような暑さの日も行列は絶えず、立ち上る湯気を見つめる人々は笑顔に満ちている。戦火をくぐり、震災を乗り越え百余年。現在は4代目の曹祐仁さんが初代から受け継いだ豚饅頭の味と人気を支える。
唯一無二の家宝から生まれる味
経木で包まれた老祥記の小ぶりな〝元祖豚饅頭〟は、押しも押されもしない神戸の名物。アツアツを頬張ると肉汁がジュワッとあふれ出て、そのおいしさに思わず2個3個と手が伸びる。多くの人をとりこにする味と食感の秘密は、まず皮にあると祐仁さんは教えてくれた。「独特の風味ともっちり感は、初代が故郷の中国から持ってきた麹のなせる技。わずかに残した生地に小麦粉と水を注ぎ足して、また生地を仕込むという作業を100年以上続けています。麹は戦時中や阪神・淡路大震災の時も守り抜いた唯一無二の家宝です」。餡も代々同じレシピで作り、材料の核となる牛肉と豚肉の合い挽きミンチは、老舗精肉店「森谷商店」による特別配合だ。
SNSや数々のメディアでも取り上げられ、その名は今や全国区。多い時で1日2万個作るという豚饅頭は毎日飛ぶように売れ、百貨店の催事にもファンが押し寄せる。それでも多店舗展開のリクエストを拒み続けるのは、「南京町の老祥記」というブランドへの思いと街への愛着が深いがゆえ。また、品質管理においても現実的ではないという。「麹は生き物なので気候風土や水によって質が変化しますし、発酵状態の見極めは職人の経験が頼り。目が行き届かなくなると商品の品質を損ねる恐れがあります」。昨日できた仕事を今日もきちんと全うし、いつ来ても変わらない味をお客さんに提供することが最も大事であり、一番難しいと祐仁さんは言葉に力を込める。
歴史ある豚饅頭を未来へつなぐ宿命
南京町の一角に、祐仁さんの曽祖父にあたる松琪(しょうき)さんがのれんを掲げたのは大正4年(1915年)。日本人好みに手を加えた中国の天津包子を豚饅頭と名付けたことに始まる。戦後、2代目の穂昇(ほうしょう)さんによって繁盛店へと成長し、3代目の英生(えいせい)さんは店の発展に尽力しながら、震災時は無償で炊き出しを行うなど、南京町の復興や観光地化にも貢献した。高校1年生の時から店を手伝っていた祐仁さんは、幼い頃から家業を日常生活の一部と捉え、自然と後継ぎとしての自覚が芽生えたと振り返る。4代目になった今は、伝統を重んじながらもあぐらはかかず、挑戦をいとわない。地域活性の一助になればと地元企業と新たな味を企画し、次世代への味の継承を目的とした食育活動にも熱心だ。「おいしいものが豊かな神戸ですが、それゆえに特筆すべき食べ物がないんじゃないかと思うんです。豚饅頭が地域特有の食文化として根付くよう、神戸市の給食で1年に1度は豚饅頭を味わってもらえる日を作ることが目標。『神戸と言えば豚饅頭だよね』と周知してもらえるようにがんばります」。そのままはもちろんのこと、カレーをかけても中華スープに加えてもよし。南京町生まれの不動の味を今一度ご賞味あれ。
プロフィール

老祥記 専務取締役(4代目)
曹 祐仁(そう まさひと)さん
1987年神戸市生まれ。7歳の時に阪神・淡路大震災で被災し、父親らの炊き出しを手伝う中で地域との結びつきや人の温かさを学ぶ。関西学院大学商学部を卒業後、パナソニックに就職し、2012年より家業に専念。「行列の先の幸せ」を常に追求し、お客さんに喜んでもらえる食づくりを実践している。
インフォメーション
曹家包子館(ソウケパオツーカン)
伝統の餡に椎茸スライスを加え、さらに旨味を高めたのが同店の椎茸豚肉包(1個100円)。「老祥記の豚饅頭と値段は同じでサイズはやや大きめ」なんだそう。味比べしてみるのもおすすめ。今年の春節祭の期間中(2月10日~12日)は曹家包子館のみ営業。
☎078-331-7726
神戸市中央区元町通1-3-7
10:00~18:30(売り切れ次第閉店)
火曜休(祝日は営業、翌日休)

取材ウラバナシ
アイデア創出のため、オフ時間は体を動かしてリフレッシュするのが祐仁さんの日課。筋トレ歴は約10年で、毎週ヨガレッスンに通うようになってからは風邪と無縁だそう。「ヨガは頭の中を無にできるのも気に入っています」